
福祉用具専門相談員っと聞いても、何のことかまったく分からない。



福祉用具ということは介護系の仕事かな。



そもそも何?
福祉用具専門相談員と言われても、有名な職業ではないので知らない人の方が多いと思います。
福祉用具専門相談員は、介護保険法に則り65歳以上の高齢者に向けて、介護ベッドや車いすなどの福祉用具をレンタル・販売する仕事です。
具体的には、高齢者の身体や住環境に合った福祉用具を選定し、生活課題を解決していくお手伝いをします。
やっぱり、介護・福祉系の仕事かぁ・・
未経験だと大変そうだし、きつい仕事なんだろうな!
未経験が大変なこと、きつい仕事であることは否定しません。ただ、福祉用具専門相談員は高齢者の体に直接触れる介護ができないため、一般的に思われている介護のイメージとは異なると思います。
介護業界でも面白い立ち位置にいる福祉用具専門相談員。
相談員の主な仕事「選定」をメインにして、業務内容を紹介していきます。
介護・福祉業界をいわゆる3Kとして、一歩足を踏み入れられないあなたには、目からウロコの内容になっています。ぜひ、参考にしてください。
福祉用具専門相談員の必須スキルである選定とは


福祉用具専門相談員は、利用者様に合う福祉用具を提案していく仕事です。膨大にある福祉用具から利用者様に適合する商品を選定するのは簡単なことではありません。
選定業務には、2つのポイントがあります。
- 利用者様の満足度のアップ
- 福祉用具専門相談員のやりがい
この2つのポイントは、福祉用具専門相談員という職業を楽しめるかどうかにかかわってきます。それぞれ、解説していきます。
1.利用者様の満足度アップ
福祉用具専門相談員の業務は
利用者様の身体の状態に合わせて適切な福祉用具を選定(選ぶ)することです。
つまり、選定力がなければ、利用者様の満足度を上げることができません。
利用者様の「今の問題に対応しつつ、今後起こり得る問題」を先回りして福祉用具を提案し、問題を解決する必要があります。幅広い専門知識が要求され、しかも利用者様が10人いれば10通りの選定方法があり正解はありません。
そのため、どんな利用者様でも対応できるように「選定力」を磨いていく必要があります。



専門相談員と言われる所以ですね。
2.福祉用具専門相談員のやりがい
福祉用具納品後の利用者様の声です。
介護ベットを利用してから、床で寝ていた時よりも立ち上がりがスムーズにできるようになりました。今までは立ち上がりに時間がかかり、トイレの失敗(失禁)がありましたが、おかげさまでトイレの失敗(失禁)が少なくなりました。
服などを汚してしまうと家族に迷惑をかけてしまうので、本当に苦しい想いをしていました。
福祉用具専門相談員の仕事は、利用者様の生活に密着しています。そのため「ありがとう」の言葉があまりにも重く、うまくいった時の喜びははかり知れません。
選定力を磨くことが、利用者様貢献につながります。たくさん「ありがとう」と言っていただくことが、やりがいになります。
福祉用具専門相談員の必須スキル「選定」は、利用者様の満足度のアップと仕事のやりがいを感じさせるものです。特別な勉強が必要なわけではなく現場で磨いていくため、誰でもチャレンジすることができます。
福祉用具専門相談員の業務内容:選定から回収まで
福祉用具専門相談員の仕事の流れはだいたい6つの工程に区別することができます。これを見れば福祉用具専門相談員のだいたいの業務内容を把握することができます。
- 利用者様宅へ訪問して商品の選定
- 個別援助計画書作成
- フィッテング(適合)・商品説明
- 契約(計画書の説明)
- 定期的なモニタリング
- 回収(引上げ)
以上、6工程が基本的な流れになります。それぞれ紹介していきます。
これにくわえて、営業活動がありますが、別の記事に記載いたします。
1.利用者様宅への訪問、商品の選定(現調)


利用者様に家の中を歩いてもらったり、トイレ動作などを確認をして、生活の課題を確認していきます。課題を把握して、安全に無理なく課題をクリアできる福祉用具を選定していく作業です。



福祉用具は利用者様の身体の状態に適合させることと、住環境に適合させないと福祉用具を使用できません。しっかり確認しましょう。
2.個別援助計画書の作成


利用者様宅で確認した課題に沿ってケアマネジャーが「ケアプラン」を作成します。ケアプランは利用者様のケアの方針を示すもので、それぞれの介護サービスはケアプランをもとにサービスを提供していきます。
福祉用具専門相談員は、ケアプランに沿って福祉用具に特化した個別援助計画書を作成する必要があります。福祉用具の立場から利用目標を設定し、目標を実現するために必要な福祉用具とその選定理由を明確にします。
室内歩行時ふらつきが見られ、転倒の危険がある。歩行器を使用することにより、ふらつきを抑制して転倒を予防したい。
○○(福祉用具名)は、軽量でコンパクトであるため、取り扱いしやすく室内の移動がしやすい歩行器です。室内での転倒予防のため、この歩行器を選定しました。
利用者様に納品した商品にそれぞれ、選定理由を記載していきます。



介護保険法に則って業務を行うので、こうした事務的な業務も正確にこなしていく必要があります。
3.フィッテング(適合確認)・商品説明
現調・個別援助計画書の作成をしてやっと、納品になります。ただ、納品と言っても単純に商品をお届けするだけではありません。また単純な商品説明をするだけでもありません。納品時に大切なフィッテングを行います。
フィッティングの重要なポイントは3つあります。
- 正しく福祉用具を利用できるか確認
- 身体に適合しているか確認
- 生活の課題を解決できているか確認
それぞれ、見ていきましょう。
1.正しく福祉用具を利用できるか確認
福祉用具は正しく利用できないと、ケガしてしまうリスクがあります。最悪の場合、死亡事故につながることもあります。
商品納品時には、商品説明と実際に利用者様に操作してもらい確認していきます。
2.身体に適合しているか確認
たとえば、四点杖の納品時に利用者様の身長に合っていなければ歩きづらいし、腰痛につながります。「こっちの方が使いやすい」と利用者様から言われますが、許容範囲外ならばしっかりアドバイスします。
3.生活の課題を解決できているか確認
福祉用具は生活課題を解決するために導入します。実際に福祉用を利用して廊下を歩いてもらったり、トイレのドアを開けるなど新しい動作に挑戦してもらいます。
うまく利用できることを確認して、初めて商品の納品が完了します。
4.契約書類の作成と説明


無事にフィッテングが完了し、商品説明もできたら契約に移ります。各社の書式に合わせて「契約書」「重要事項」「個人情報」などの契約を取り交わします。
あわせて、事前に作成した個別援助計画書に同意をいただき、署名してもらいます。



福祉用具の知識だけでなく、契約書の取り交わしなどの業務も覚える必要があります。
5.定期的なモニタリング
福祉用具は納品して終わりではなく、年に2回半年に1回のペースでモニタリングする必要をします。
定期的なモニタリングは以下の2つ観点で行います。
- 福祉用具に不具合がないか点検する
- 利用者様の身体に適合しているか確認する
それぞれ確認していきましょう。
1.福祉用具に不具合がないか点検する
福祉用具のネジが緩んでいないか、異音が発生していないかなど物理的な不具合がないか確認していく作業です。福祉用具利用時に、商品の不具合で転倒等の事故が生じたら大問題です。しっかりと点検をしていきます。
2.利用者様の身体に適合しているか確認する
利用者様の身体の状態は変化しやすいため、福祉用具を納品した時の状態より良くなってたり、逆に悪くなっている場合があります。納品時と変わらず福祉用具を継続使用していくべきか、再選定すべきか確認します。
福祉用具レンタルの最終的な目標は「卒業」にあります。身体の状態が良好になり、福祉用具を使用しなくてもいいとなれば、回収の提案をする必要があります。
6.回収(引上げ)
利用して頂いた商品を回収する業務です。回収にはポジティブな理由もあれば、ネガティブな場合もあります。回収時の利用者様対応は気をつけましょう。
- 元気になり福祉用具が不要になった。
- 自宅での介護が難しくなった。(ご入所)
- ご入院、ご逝去された。
利用者様と接していれば、生活の一部を感じます。家族構成や家族仲など個人的な情報を垣間見ることもあります。良くしていただいた利用者様の不幸は、心が折れるので覚悟が必要です。
介護の仕事なのに直接介助できない!介護業界における福祉用具専門相談員の役割とは


福祉用具専門相談員の資格だけでは、利用者様に直接触れて介護をすることができません。



介護の仕事で利用者様に直接介護できないなんて
致命的では?
結論から言うと、他の介護サービスとは異なります。
環境整備することが福祉用具専門相談員の役割です。
具体的にはどういうことでしょうか、2つポイントがあります。
- 利用者様や家族、介護職員の介護環境の整備をする。
- 手すりの取付など住宅環境を整備する。
福祉用具専門相談員は、縁の下の力持ちの裏方に徹する必要があります。
それぞれ見てみましょう。
1.利用者様や家族、介護職員の介護環境を整備する。
介護環境を整備は、利用者様やご家族、介護職員の負担軽減につながります。
利用者様視点
福祉用具を活用することで、できなかったことを安全にできるようにサポートをしていきます。身体の負担を軽減させて動きやすい環境を整えます。
家族や介護職員の視点
福祉用具専門相談員ができることは、介護者の負担軽減になります。
たとえば、介護ベットの導入には主に2つの目的があります。(介護ベットは床からの高さや背もたれの角度を電動で調整できるベッドです。)
- 利用者様が安全に立ち座りしやすいようにするため。
- ベッド上での介護は中腰になるので、介護者が腰を痛めないにするため。
介護負担はこうした身体的な負担だけではありませんが、介護環境を整備して間接的ですがサポートしていきます。
私たちの役割は、介護環境の整備だけではなく、物理的に住宅環境の整備もします。
2.手すりの取付など住宅環境を整備する。
福祉用具専門相談員の仕事には、トイレ内に手すりを取り付けるなどの住宅改修があります。



ここに、手すりがあれば
自力で立ち上がれるのに・・。
こうした問題を解決します。
介護保険を利用して住宅改修できる工事の種類は、手すりの取付含めて6種類あります。
福祉用具専門相談員は、福祉用具の知識や住宅改修の知識を活用して、間接的ですが利用者様や家族、介護職員のサポートをします。
3Kのような仕事はするの?
介護・福祉業界をいわゆる3Kとして、一歩足を踏み入れられないあなたの不安材料こちらでしょうか。
- 介護技術が未熟だと利用者様をケガをさせてしまう心配。
- 排泄や入浴介助に抵抗がある。
- 勤務時間が不規則
福祉用具専門相談員は直接的な介護をすることができないので、排泄介助や入浴介助などはできません。直接介護に抵抗がある人には、取っ掛かりしやすい職種かもしれません。
どちらかと言えば、福祉用具専門相談員は一般的な営業職に近いです。そのため、勤務時間についても不規則ではありません。



しかし、数字に追われます。
月の売上目標に対して、達成しているかを常に確認されます。介護業界にはないイメージであるため、このギャップが付いてこれず退職する人もたくさんいます。
直接的な介護はありませんが、毎月数字に追われる職種になります。
あなたの考え方や肌感覚に合わせて慎重に考えることをおすすめします。
まとめ:基本だけど奥が深い選定スキル


福祉用具専門相談員の基本でありながら、やりがいにつながる「選定」を中心に業務内容を解説してきました。
選定は基本的な業務だからこそ、営業マンの力量の差が如実に表れてきます。
そのため社名ではなく、あなたの選定スキルによって活躍の場が広がります。
一般的な営業職に近い職種のため、介護業界としては面白い立ち位置にいます。正直、介護職を専門に挑戦していきたい人にはおすすめできません。
自分の選定した福祉用具が利用者様の生活水準が向上させることができた。利用者様や家族と一緒に喜べることができた時は、最高にやりがいを感じます。利用者様や介護職員の方々の縁の下の力持ちになって活躍したい人にはおすすめできる職業です。
福祉用具専門相談員の仕事内容を確認したい方の参考になれば幸いです。
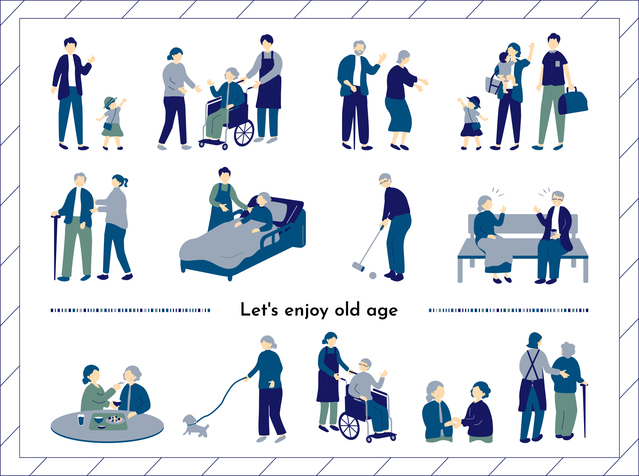
コメント